有機ELディスプレイで培ったインクジェット技術を活かす
パナソニックグループが次世代型太陽電池として期待されるPSCの研究開発に着手したのは2014年のことだ。2015年からはNEDOの開発プロジェクトに参画。2020年には30㎝角モジュールをベースにした開口面積802㎠の実用化レベルで当時世界最高の変換効率17.9%を達成した(2024年2月現在18.1%に向上)。
こうした実用化レベルでの高効率化を支えたのはパナソニックグループのさまざまな技術の集積であるが、とくに有機ELディスプレイ生産で用いたインクジェット塗布技術がそのまま開発に活かされたという。ガラス基板の上に、いかに薄く、均一に材料の有機化合物を塗布できるかどうかが高効率化、大面積化のカギを握っているからだ。
![製造プロセス[参考イメージCG]](https://www.kankyo-business.jp/uploads/2024/04/16/WBIQS86ZVxBPbQznLSP6LKcyxeCmSTk4CGuyJmaa.jpg)
製造プロセス(参考イメージCG)
「大面積の透明電極付ガラス基板にレーザー加工でカット・パターニングし、インクジェットで発電層を均一に塗布しさらにレーザー加工でカットする。当社のインクジェットを用いた大画面・サイズフリー塗工技術とレーザー技術を組み合わせることで、サイズや透過度、デザインなどの自由度を高め、カスタマイズにも対応することができます」
たとえば、レーザーで塗布部分を飛ばし、元の透明なガラスに戻すこともできるし、透過度を2割、4割に設定することもできる。さらにガラスの上部は視線を遮らないように透明度を高くし、足元に下るに従い遮蔽性が高まるといったグラデーション状のデザインも可能だ。まだ数値を算定していないが、窓から入る日差しを電気エネルギーに変換するので、遮熱による省エネ効果も高いという。

製造プロセス(参考イメージCG)

発電するガラス(参考イメージCG)
シリコン系並みの耐久性を実現し製品化を目指す
今年4月には1m×1.8mの大面積のガラス建材一体型PSCの試作ラインも立ち上げる。大面積化することで生産コストも下がり、デザイン性も向上する。さらに2024年度末には大面積モデルでの実証試験を開始する見込みだ。またPSCは水分や酸素などに弱いとされるが、劣化物資を遮断し、大面積化とともに技術課題の一つである耐久性も高める。
金子氏は「我々は製品化へのファーストステップとして、20年後の劣化率をシリコン系太陽電池同等レベルに抑えることを目差しています。また発電コストについては、NEDOのグリーンイノベーション事業が2030年までにシリコン系と同等に14円/kWhの達成を掲げていますが、コストを下げるには高い変換効率を大面積でも維持し、量産体制を確立することが欠かせません」と事業化を視野に入れる。
金子氏はお客様の要望に応え、高効率で耐久性を備えたガラス建材一体型PSCを提供できるのは、おおよそ4,5年先になるだろうと話す。その市場は4桁億円(1000億円単位)の規模に成長すると見込んでいる。
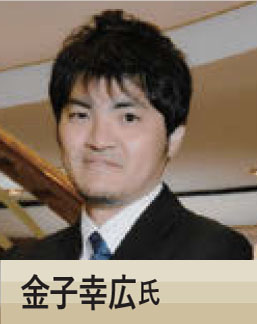
金子幸広氏